この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
たまに、子供の転落事故という悲しいニュースが流れてきて、自分の子供ではないけどとてもつらい気持ちになります。
そこで、自戒の意味も込めて、『子供の窓やベランダからの転落事故はなぜ起こる?原因と防止対策まとめ』について話していきたいと思います。
- いまお子さんがいる家庭
- これからお子さんが生まれる家庭
- 孫がいる・孫が生まれる予定の人
目次 (クリックで飛ぶ) 閉じる
まずは子供の柵を登る能力を見て危険性をチェック

上記のニュースを見て、子供の柵を登る能力がどれくらいあるのか調べてみました。
・条件:ベランダの手すりに見立てた高さ110cmの器具 (建築基準法が110cm以上)
・4歳の子供→約7割が登りきれた (最短10秒程度)
・6歳の子供→全員が登りきれた (最短3秒)
・2歳の男の子→最短15秒で登りきれた
また、上記動画よりNPO法人 Safe Kids Japanによる実験の結果をまとめました。
・条件:120cmの柵を30秒間で登れた子供
・3歳→65.7%
・4歳→72.5%
・5歳→90.2%
小学生にも満たない年齢の子のほとんどが短時間で登れたことにも驚きですが、2歳の子でも少し目を離した程度の時間で登り切れてしまうのにはもっと驚きです。
子供の転落事故の防止・対策のために親ができること
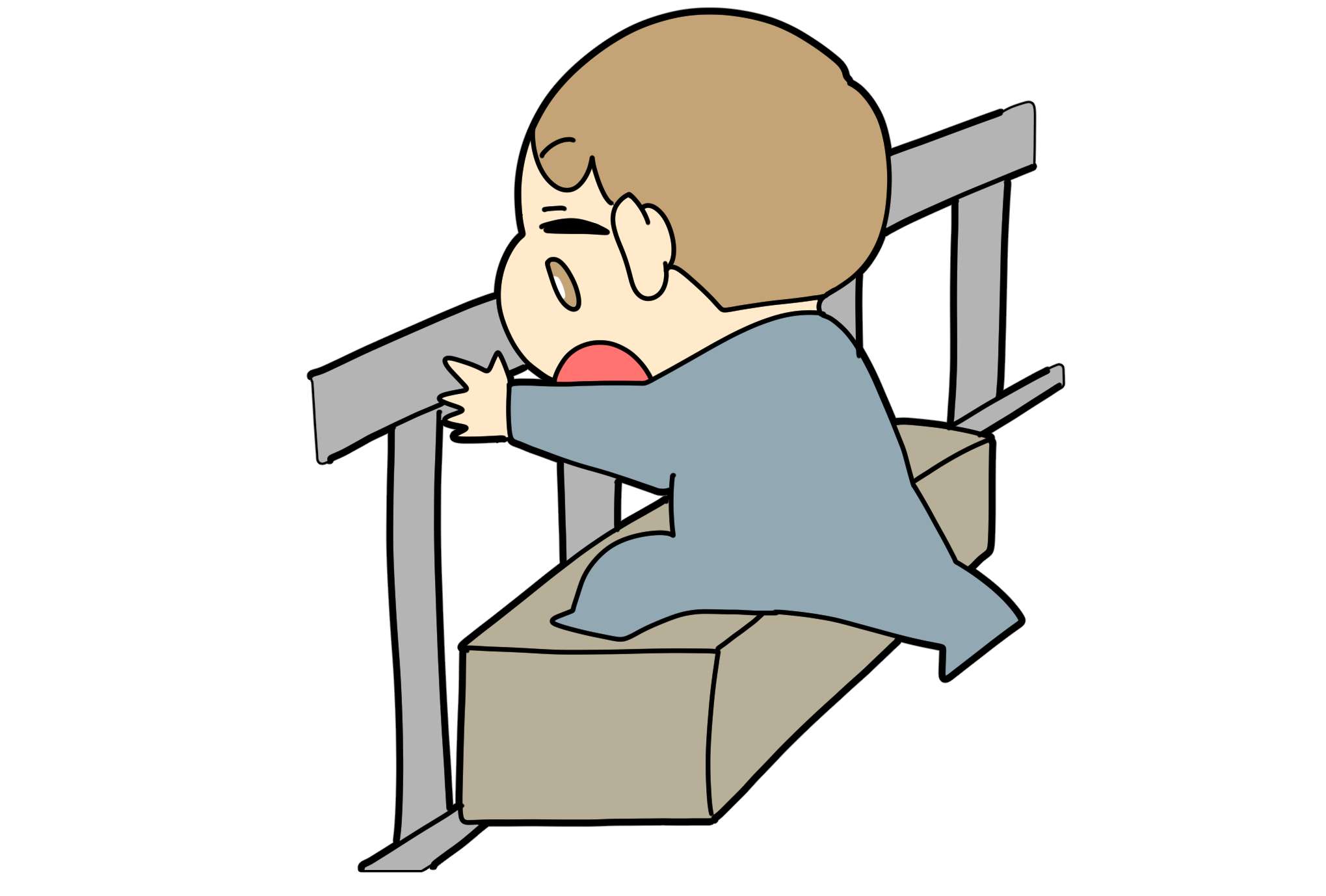
ここでは、『子供の転落事故の防止・対策のために親ができること』についてまとめました。
上記のデータを見ると、もう「子供は全員が自力で柵をよじ登る能力がある」「一瞬でも目を離したら転落する危険性がある」と思って対策を練った方が良さそうです。
対策①:窓やベランダ近くによじ登れるものを置かない(子供が窓を開けないための対策)
子供の転落事故の7割以上で子供がよじ登れる足場になるものが置かれています。
なので、基本的な対策として、子供が大きくなるまで窓の近くやベランダには物を置かないを徹底しましょう。
・窓の近くにソファやベッド、本棚などの家具を置かない
→大人用のベッドに寝ていた0歳児が、近くの窓から転落する事故もありました。
→本棚は高さがあっても棚板を階段のように登って窓に辿り着く場合もあります。
・ベランダにイスやプランダーなどを置かない
・ベランダにある室外機は60cm以上離す
→離せない場合は柵で囲うらしいが、柵を使って登る気がするので開けない方が良いと思う
対策②:補助錠を子供の手の届かないところに付ける(子供が窓を開けないための対策)
親が窓を開けなくても子供が自分で窓を開けて転落するパターンもあります。
なので、子供が手の届かないところに補助錠を付けると安心です。
これは空巣対策にもなります。
・手が届かないところに補助錠(2個目の鍵)を取り付ける
対策③:窓を開けたらアラームが鳴るようにする(子供が窓を開けた場合の対策)
カギを子供の手が届かないところに複数つけても、イスを持ってきて開けてしまう可能性があります。
なので、子供が窓を開けた場合の対策として、窓を開けたらアラームが鳴るタイプの補助錠を付けましょう。
・警報アラーム付きの補助錠を付ける
対策④:窓ストッパーを付ける(子供が窓を開けた場合の対策)
もし窓を開けて警報アラームがなったとしても、その音に大人が気付かなかったり、その音を子供が無視して飛び降りてしまったら大変です。
なので、「窓を開けても転落を防げるよう」、窓の開き幅を小さくする窓ストッパーを付けると良いでしょう。
・窓ストッパーを両側に付ける
※付けてからどちらから開けても開き幅が小さくなるかを確認しましょう。
対策⑤:カギの閉め忘れ防止用のシールを張る(大人のうっかりへの対策)
子供が窓を開けられないようにしても、大人が空気の入れ替えなどで窓を開けて、窓は閉めたけどカギを閉め忘れたままでは意味がありません。
そうならないよう、窓の近くにカギの閉め忘れ防止用のシールを張るといいでしょう。
・カギの閉め忘れ防止用のシールを張る
対策⑥:窓は開けない(親の意識の問題)
窓を開けたら気付かないうちに子どもが外に出る、親が窓・カギを閉め忘れた結果子供が開けて外に出ることも考えられます。
なので、そもそも子供が大きくなるまで窓を開けないという意識をするのが良さそうです。
しかし、窓を開けないと洗濯物が干せなかったり、空気の入れ替えがうまくいかないこともあるので、下記のような対策をするのがおすすめです。
・洗濯物を外で干さない・部屋干しに切り替える
・部屋干し用にドラム式洗濯乾燥機や除湿器を買う
・空気清浄機を買う(空気の循環がなくても空気を綺麗にする)
・24時間換気システムのフィルターをこまめに交換する(空気の循環を良くする)
対策⑦:手すりの形状に気を付ける
手すりの仕様がヨコ桟状でよじ登りやすかったり、手すり同士や下の隙間が大きいとすり抜けやすく事故に繋がります。
なので、新しく住む家・部屋の場合は手すりの形状を考慮するか、その他の対策を徹底すると良いと思います。
・タテ桟状のタイプにする
・手すり同士の隙間を11cm以下・下の部分の隙間を9cm以下にする
対策⑧:網戸が劣化がしていないか確認する
劣化した網戸に寄りかかり、突き破って転落する事故もありました。
特に築年数が古い建物では網戸も劣化している可能性があるので、そこも確認しましょう。
・網戸が劣化していないか確認する。
※劣化していたら新しいものと取り換える
対策⑨:マンションの一階に引っ越す
マンションの一階に引っ越すことで、そもそも転落するということをなくすことができます。
対策⑩:窓を開けやすい5月・10月は特に注意
子供の転落事故、は寒さが落ち着いた5月頃や夏の暑さが落ち着いた10月頃に特に多くみられます。
年間を通して気を付けるのはもちろんですが、窓を開けやすい時期は特に注意しましょう。
まとめ:子供の転落事故を防ぐには複数の対策が必須

以上が『子供の窓やベランダからの転落事故はなぜ起こる?原因と防止対策まとめ』でした!
子供の転落事故の例をいくつか見ましたが、どれか一つをやってれば防げるという簡単な話ではなく、子供の転落事故を防ぐには複数の対策が必須だと感じます。
下記に子供の転落事故についての参考サイトを載せましたので、痛ましい事故が二度と起きないよう、みなさんで気を付けていきましょう。
・YouTubeチャンネル TBS NEWS DIG Powered by JNN – 『マンションなどで起きた子どもの転落死亡事故 7割以上窓やベランダの手すり近くに“足場になる物”が 消費者庁 事故防止のチェックリスト公開』
・YouTubeチャンネル TBS NEWS DIG Powered by JNN – 『ベランダの柵を高くしても子どもの転落は防げない?130センチの柵を登れる5歳児は83%』
・YouTubeチャンネル 東海テレビ NEWS ONE – 『窓にはストッパーに鍵も…2歳の双子がマンション7階から転落死 なぜ事故は起きたのか 春に増える子供の転落』
・消費者庁 – 『「⼦どもの転落事故」防⽌のためのチェックリスト』
・東京消防庁 – 『こどもが住宅等の窓・ベランダから墜落する事故に注意!』
・政府広報オンライン – 『ご注意ください!窓やベランダからのこどもの転落事故』










